文学大賞 本編部門06
作者: T・U
私が完全に家から出られなくなったのは23歳の時だったと思う。
自分の身に起こったことでありながら「思う」などと曖昧な表現を使うのは、言葉通り、私にも正確な時期がわからないからだ。
私は中学1年の時に不登校になった。その経験が発端だったと言えるのかもしれないが、不登校になり直ちに社会との接点が絶たれたわけではなかった。
不登校になってしばらくすると、身体に様々な異変がおこるようになった。眩暈、腹痛、起きられない、眠れない、不潔なものに対する過剰な恐れ、食べられない飲めない、また反対に食べ過ぎる等。次々とやってくる症状をどうにかやり過ごすうちに、私の10代の時間は過ぎていった。
そうして気づけば一歩も家の外に出ることが出来なくなっていた。
原因は色々あったはずで、それは例えば中学生時代のいじめから生まれた他者への恐怖だとか、年頃になっても相応の装いが出来ないことに対する羞恥心だとか、拒食・過食症を患った際につくってしまった虫歯の治療が怖いだとか(治療者に不審に思われるのが怖い等)、世間への負い目だとか、幼少期から持っていた死に対する恐れだとか……さまざまに思い浮かべることが出来るが、今となってはそのどれ一つとして決定的なものはなかったような気がしている。
私は不登校になってからも場所は限られるものの外出はでき、10代の間は本屋など、それなりに行きたいところへ出かけられていた。ところが徐々に不安や苦手な状況が増えていき、それらが結びついて悪循環が起こり、外に出るのは困難になっていった。一例を挙げると、伸びた髪が恥ずかしいという理由だ。私は元来美容院で髪を切るのが苦手だったのだが、幼い頃は身なりに無頓着だったため、ほとんどその機会を持たずに済んだ。しかし、10代の終わりにさしかかると人目が気になるようになり、とりわけ髪が整えられないことに強い羞恥を感じるようになった。外出できるようになるためには苦手な美容院で髪を整える必要があるが、そもそも「現状が恥ずかしくて」人前に出られないのであり、美容院まで赴くこと自体ができないため、話は振り出しへと戻ってしまう。そのような状態だったので、劇的な何かが起こっただとか、何かを決めて「ひきこもる」状況に至ったという覚えがなく、それがいつ始まったのか当事者である私にもわからないのだ。気づけば家から出られなくなっていたというのが私の実感だった。
何を試みたところで八方塞がりに思えて、私は身動きがとれなくなった。いいわけがましく聞こえるかもしれないが、私の置かれた状況、不安が不安を呼ぶ悪循環は自分にとって理解しがたい事態であり、ましてその不安の堂々巡りから自力で脱する方法などわかりようもなかった。
そうして動けずにいる間にも、時間はどんどん過ぎていく。閉塞感の中で焦り、恐怖に駆られ、そしてまた果てのない不安に陥り……一歩踏み出す糸口すら見えず、暗闇の海にひとり投げ出されたような、そんな感覚だった。
死ぬしかないのではないかと思い詰め、自分の考えの恐ろしさに震えるような時は、ネットでの買い物に逃避した。物を注文し、品物が届くまでの間は、とりあえず「待つ」という行為が恐怖心を誤魔化してくれる。私にとっては注文した品はどうでも良く、ただただ待つことが一時の救いとなった。しかし買い物依存という、新たな悪循環の輪も生まれてしまった。買う・待つ行為が目的であって物自体には興味がないので、届いた服や本は部屋の隅に積み上げられていくばかりとなり、自室は足の踏み場もないような状態になっていった。
私は自分が恥ずかしくてたまらなかった。家から出られず、昼夜逆転した生活を送り、現実からは物を買うことで逃避し、両親が与えてくれる金を浪費して、あまつさえ部屋をひどい有様にしてしまう。だが、いくら自分を責めても身体は動いてはくれない。
そのうち私は、やり場のない焦燥を母にぶつけるようになった。
助けてくれ、どうすればいいのか教えてほしい、という要求だけでなく、傷つけるような言葉を口走った日もある。そのたびに自己嫌悪に陥る。それでも母に言葉を投げつけずにいられなかった。
追いつめられてゆく中で外部に助けを求めることも考えはしたものの、当時地方では当事者支援の情報が乏しく、実際に利用できる社会的資源も限られていた。私は精神科医療などの、強制介入のようなものでしか現状を打開する方法がないのではないかと感じはじめていたが、それを頭の中であっても言葉にするのは怖かった。形となってしまえば後戻りができなくなるような気がした。私は感情を母にぶつけながら、決定的な言葉を避けていた。今にして思えば、察してほしかったのだと思う。自分で責任を負うことを避けながら、母には気づいてほしいと思っていたのだ。そこには、母なら気づいてくれるはずだ、理解してくれて当然だという、過ぎた甘えがあった。そのような感情の境界の曖昧さは、自分と母の同一視であっただろうし、あるいは、幼児がそうであるように、母に全知全能の神を見ていたのかもしれなかった。
毎日毎日不毛なやりとりを繰り返す、変化のない日々は澱んだ沼のようだった。
しかしある春の日、突然、水面が大きく波を打つ出来事がおきた。
母に病気が見つかったのだ。
退職を間近に控えていた母が念のためにと受けた健康診断で、乳がんが見つかったのだという。母は一見普段と変わらないようで、けれど動揺が無いはずはなく、私は言葉をかけることを躊躇った。泣き言や自分勝手な言葉ばかりぶつけてきた私に何が言えるというのだろうか。私はその時になってはじめて、母も一人の弱い人間だと云う当たり前の事実に気づいたのだった。
幸い母の病気は初期で、手術を含め3日の入院で済むという。しかし、家の様相はにわかに変わった。
父も母も入院の準備や手続きの諸々に追われ、帰省した妹も忙しく手伝う、という毎日だった。それから実際に入院し手術となると、妹と父は病室に通って母を助けた。そこに私の出来ることは何もなかった。数少ない役目である家事をしながら、家で母の帰りを待つしかない。母に対して何の力にもなれない自分がはがゆく、情けなかった。
そして、恥ずかしい話だが、この期に及んで私は、怖かったのだった。
自分はこれからどうなってしまうのだろう。私は母がいなければ何一つできない。だが、母には母自身のすべきことがある。私は自分で自分の始末をつけなければならない。
とにかく外に出なくては。強くそう思ったのを覚えている。
翌日私は、伸び放題の髪を束ねてニット帽で隠し、早朝、まだ日が昇りきらないうちに家の門を出た。
母は無事に退院した。しかし、以前の日々が戻ったわけではなかった。母は病気の再発予防のために服薬と定期的な検査が必要な身であり、胸部の手術の影響で利き腕はまだ本調子には遠かったので、私が家事を手伝ったり、ときには母に代わって務める機会が増えた。何より変わったのは、私と母との心理的な距離だったろうと思う。私は、もう母が私のことをわかってくれて当然だというような、全幅の安心を母に求めることは出来なくなった。それは心細く、寂しかったが、同時にやっと自分を個としての「わたし」と認識できるようになった気がした。親からの情緒的自立が青年の発達課題であるのなら、私の青年期は30代も半ばを迎えてようやく始まったといえるのかもしれない。
そののちも紆余曲折あったが、私は今もどうにか生きていて、ほとんど毎日外へ出かける。しかし私は現在も厚労省の定義するところの「社会的ひきこもり」であるし、自立しているなどといえる状態にはほど遠く、したがって世間一般の感覚からすれば現状は「回復」とは見做されないのかもしれない。今もまだ、私を苦しめた不安が完全に消え去ったわけではなく、死への恐怖など、年を経た分だけ重みを増したものもある。正直に言えば、今も私は変わらず悩み続けているし、不安から解放されることはこの先もないのではないかと怯えている。その一方で、家から出られずに死ぬことを考えていたかつての日々を思えば、毎日少しずつでも何かができ、外に出たいときに出られるいまは、夢のようでもある。
以上は私の個人的な体験であり、ひきこもり当事者の手記としてもなんら普遍性を持たないのかもしれないが、そのような私自身についての事象を書き連ねたのは、ひとつには自分のために書きたいという欲が生まれたからだ。最近祖母を見送ったこともあり、身内の死を通して、自分の生き方や人の生死というものを改めて考える場を得、どんどん遠ざかる過去について書き残しておかねばならないと思うようになった。拙くとも、私の感情や経験を書けるのは私しかいない。
ともすれば忘れてしまいそうになる、今があることの喜び、家族や周囲への感謝、そしてどう生きたいかについて考えることを心に留めておくために書きたいと思ったのである。
Opinions
Join the Discussion
コメントを投稿するにはログインしてください。
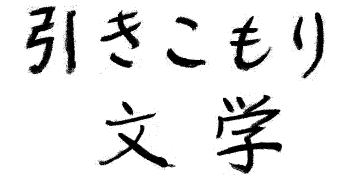


Post comment
端正な良い文章です。自分のこれまでの軌跡が素直に表現できています。
PermalinkPost comment
読みながら、なぜ人間は(もちろん自分自身も)他者に理解されたいと願ってしまうのだろう、そんなことを思わなければ楽なのに、と考えてしまいました。
Permalink「書きたいと思った」と締めておられるので、心のままに綴られた文章なのかと思ったのですが、一度も引っかからずにスーッと読んでしまったので、もしかしてかなり練られたものなのでは、と愚察しております。
推敲の回数に関わらず、何年も感情をご自身の中で巡らせていらしたでしょうから、とても苦しかっただろうな、と思わずにいられませんでした。